

上の動画は結果論である、と前置きして始めます。
避けて殴る
カネロやタイソンが攻撃を成功させるパターンの一つを抽出しました。
リーチで劣る場合は
プレッシャーをかける→相手を引きつける→殴る
は、成功確率の高い一つの形だと考えられます。
タメ→踏み込む
相手よりリーチが短いことは、この準備の点で相手より不利になると考えられます。
カネロとタイソンはこの部分を相手にやらせることで不利を克服していると考えられます。
簡単に例えるなら、後出しジャンケンです。
もしもあなたが身長が低いなら、上記の不利を克服する為の後出しジャンケンは、どのような条件を満たせれば成立させられるのかを、また、どのような練習ならそれを習得できるのかを考えることは価値があると思います。
例えば、タイソンのボクシングを要素ごとに分解してみるとか。
まだ誰も気がついていないタイソンの秘密があるかもしれません。
「誰にも見えないものが自分だけに見えるかもしれない」と、自分で自分を楽しませる視点を与えてることも上達のコツです。
後出しジャンケン
根本的な話をするなら、後出しは戦略上は非常に有利です。
グーチョキパー(≒選択肢)が揃っている、かつ相手も同じ条件なら、後出しジャンケンは負けません。
僕と同世代で遊戯王をやっていた方なら知っていると思いますが、手札、墓地(≒選択肢)肥やし戦略は強い。大会の上位はその傾向がありました。
※今は分からん
メイウェザーなどの一流が試合前に「どんな状況にも対応する」と強調する傾向を感じたことはありませんか?
彼らは真理を話しています。
対応力≒手札
後出しできる奴は論理的には負けない。
閑話休題。
脱線したので話を戻すと、本質的には、カネロやタイソンは相手が長身かどうかなどは考えていないと考えます。
誰にでも後出しジャンケンをしているだろうと考えられます。
カネロやロマゴンは序盤に相手の出方を伺う傾向にあります。特に第一ラウンドはディフェンスに専念します。
本能的に合理的な戦略を選択しているのだと思います(後出し)。

戦略を構成する要素に分解
「後出しジャンケンだ!」の後に僕らが考えるべきは、それが必然として導かれる構造に視点を向けること。
(避けてカウンター…)
実力差があるならこれでも成立するでしょうが、本気で鍛えたボクサー同士のコンマ何秒を争うような戦いにおいては、そんな悠長なやり方は通用しません。
つまり、タイソンやカネロの戦略を必然として構成している要素は何か?を考ええ、それを練習の方法に落とし込む必要があります。
例えば、避けた力を即座に床反力として推進力へ変換できるのは何故か。
あるいは、ディフェンスを担保する姿勢はどんなものが考えられるか。
そもそも、何故、彼らは敵を追い回すような構図に持ち込めるのか。
※何故、相手は腰が引けているのか
カネロやタイソン、及び、あなたが参考にしているボクサーの戦略を構成している要素は何か、を考えることでそれに近づくことができます。


結論。「ゲーム」を有利にする条件は何か。
後出しジャンケンが必然として起こるような戦略、技術体系を考え、また、それが必然として獲得される練習を考えるべし。
まずは、自分が見ざしている世界を構成要素に分解してみる。
トライアルアンドエラーを繰り返すことで徐々に霧が晴れてくる。


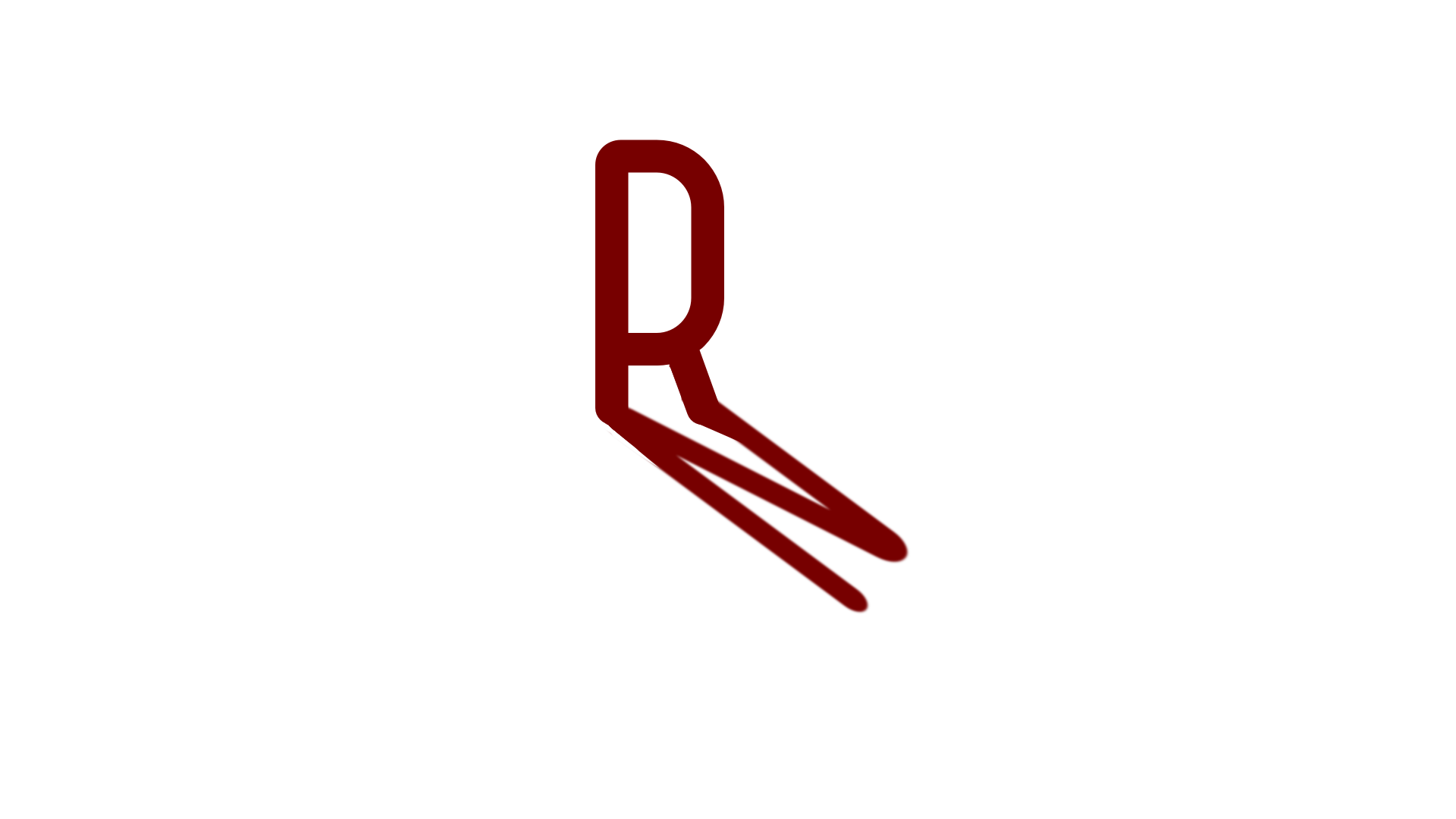
コメント