等差級数
等差数列
等差数列の初項を $a_{0}$ とし、その公差を d とすれば、第n 項 an は
$\displaystyle a_{n}=a_{0}+nd$
であり、一般に
$\displaystyle a_{n}=a_{m}+(n-m)d$
と書ける。
初項はn=1なので
$a_{1}=a+(1-1)d=a$
公差2,n=1m=3なら
$\displaystyle a_{n}=a_{m}+(n-m)d$(公差数列定義)
$\displaystyle a_{1}=a_{m}+(1-2)d$(代入)
$\displaystyle a_{1}=a_{m}+-1・d$(加法逆元)
$\displaystyle a_{1}=3+-1・2$(代入)
$\displaystyle a_{1}=3+-2$(マイナス乗法)
$\displaystyle a_{1}=1$(加法逆元)
正しく導出されました。
次はnまでを足した等差数列の部分和。求めます。
等差数列の部分和の導出
公差1の等差数列$x_{n}$(≒自然数)をk=10まで足すと
$x_{1}+x_{2}+x_{3}…x{10}$
この式は交換法則で順序を入れ替えて、
$=(x_{1}+x_{10 })+(x_{2}+x_{8})…$(交換法則と結合法則)
と変形できます。
また、()で結合した加法は、それぞれ同じ結果(=11)になります。
※5(=中央)で折りたたむと点が重なる
10番目を選んだ場合は
$10+1=x_{9}+x_{2}=11$
8番目を選んだ場合は
$8+3=x_{8}+x_{3}=11$
以上の論理をn個の数列に敷衍します。
n個の項、初項a、公差dの等差数列のk番目の項は
$a_{k}=a+(k-1)d$(等差数列定義)
これと対になるのは、n-k+1番目の項です。
※中心で折り曲げると、終点からkまでの差、始点からn+1までの差が一致する
また、$a_{k}+a_{n+k+1}$と同値の組を$\frac{n}{2}$個作れます。
よって公差d、初項aのn項の等差数列の部分和は
$\frac{n}{2}・(a_{1}+a_{n})$(仮定)
$=\frac{n}{2}・(a+a+(n-1)d)$(等差数列)
$=\frac{n}{2}・(2a+(n-1)d)$(加法)…等差数列部分和
例題
1から10までの等比級数は
$\frac{10}{2}(2+9)・1=55$
となります。
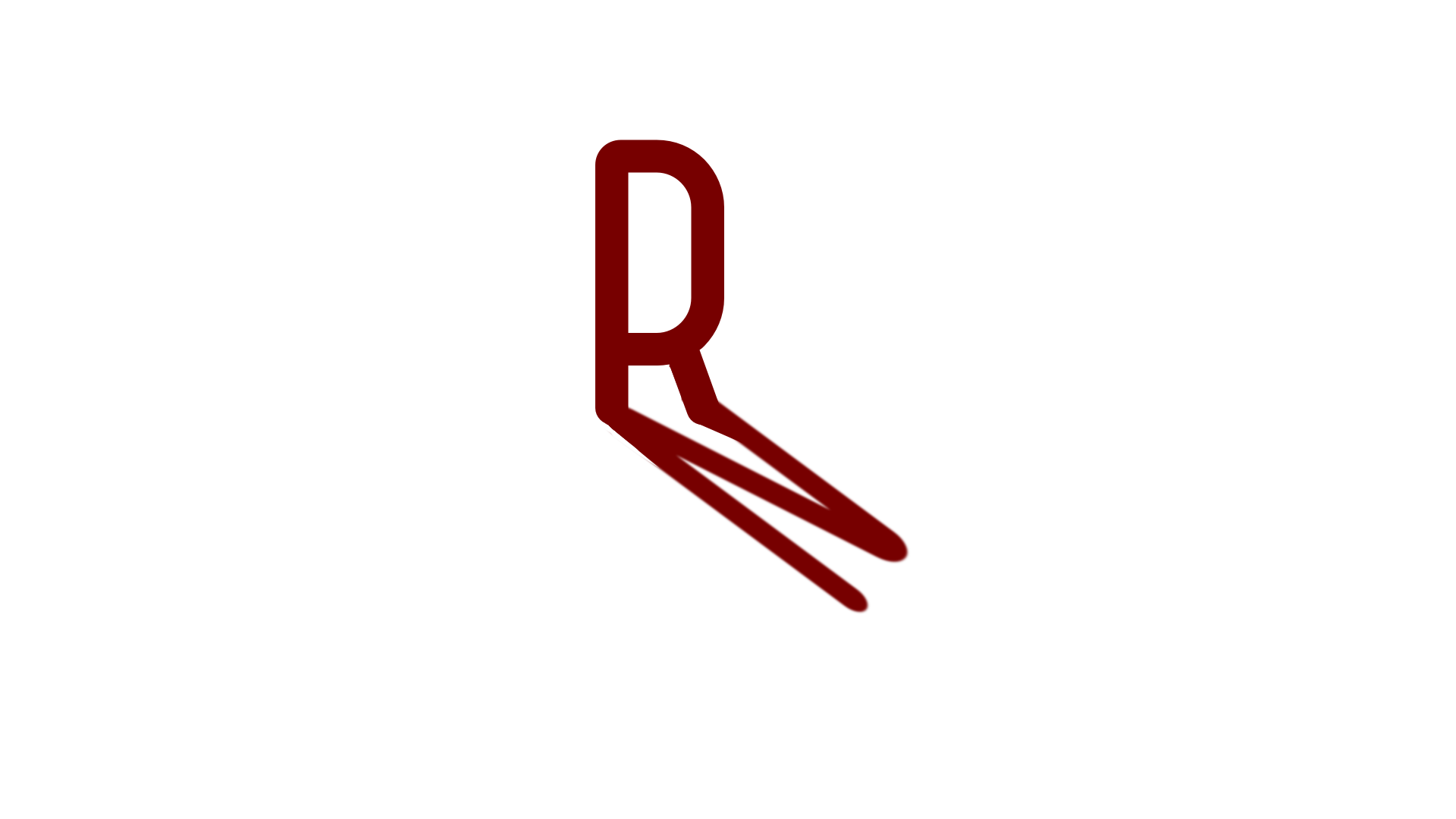

コメント