指数が分数のべき乗
$a^{\frac{y}{x}}$
これを考えます。
分かりやすいように具体的に。
$2^{\frac{1}{2}}$は
$2^{1}$(仮定)
$2^{2・2^{⁻¹}}$(乗法逆元)
$2^{2・\frac{1}{2}}$(分数定義)
$(2^{\frac{1}{2}})^{2}=2$(指数法則)
$(2^{\frac{1}{2}})=\sqrt{2}$(指数法則)
$2¹=2→2^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$(→導入)
2乗して2になる数なので、$2^{\frac{1}{2}=0.5}=\sqrt{2}$です。

日常的にこのような推論は行わないので強烈な違和感があります。
一般化。
$a^{1}$(仮定)
$a^{n・n^{⁻¹}}$(乗法逆元)
$a^{n・\frac{1}{n}}$(分数定義)
$(a^{\frac{1}{n}})^{n}$(指数法則)
$a=(a^{\frac{1}{n}})^{n}=\sqrt[n]{a}^{n}$(同値関係)
つまり
$a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}$
分子が1以外なら
$a^{\frac{x}{n}}=(\sqrt[n]{a})^{x}$
2乗して2なるのが$\sqrt{2}$
3乗して2になるのが$\sqrt[3]{2}$
気持ち悪い数。
ピタゴラス「ねぇ、誰が好き?ワタシは有理数。かっこよくない?優しいし。」
ヒッパソス「私は√2…。ミステリアスなのが良い。」
ピタゴラス「…マジ?√2は無い。アイツは無理。」
√2 (ルート2) は、1辺が1の正方形の対角線の長さであり、ピタゴラスの定理から導き出される無理数です。ピタゴラス学派は「すべての数は分数で表せる」という信念を持っていましたが、この√2の発見により、その信念が否定されることとなり、数学の歴史において重要な転換点となりました。
これは、当時「すべての数は分数で表せる」と信じていたピタゴラス学派の根本思想と矛盾するものでした。
伝説では、この無理数の存在を証明した教団のメンバーが秘密を守るために殺されたとも言われています。
引用AI


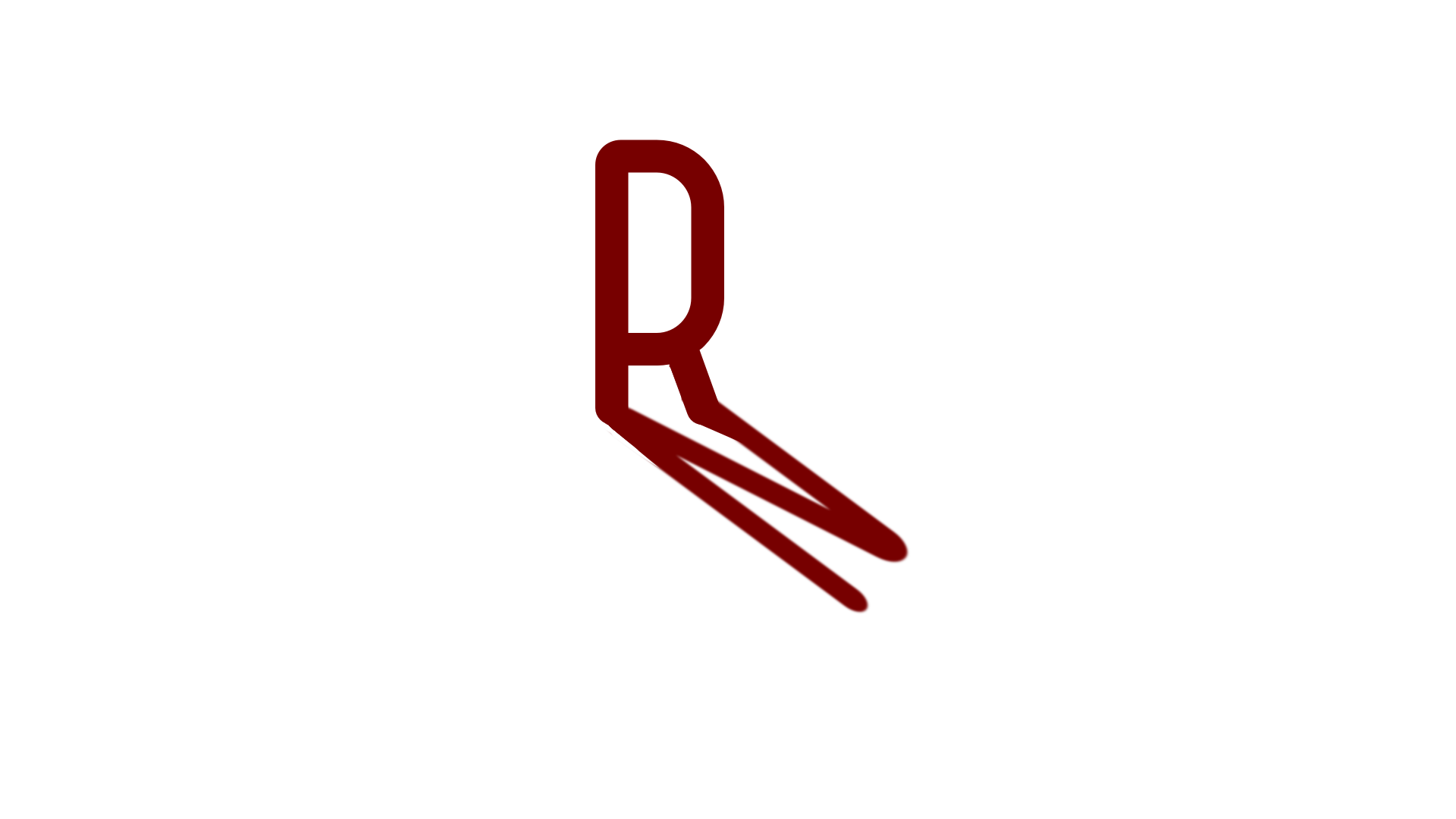
コメント