
カウンターが上手くなる為には、カウンターが”起こる”論理的な構造を考察し、それを処理可能な手続きにまで落とし込む必要があります。
カウンターの構造が分かれば、そこから逆算し「それを習得するにはのどのような練習をすべきか?」と自然かつ詳細に連想が働くはずです。
「天才」を正確に定義できれば、そこまでの詳細な地図が手に入るのと同様。
仮に欲しい技を獲得する手続きが開発できたら魔法のようだと思いませんか。

メイウェザーの立ち方
冒頭の動画で示したように、メイウェザーのカウンターを構成している要素は大まかには
1.頭を遠くする
2.フィリーシェル(L字ガード)
だと考えられます。
上記をさらに言及すると
1.頭は遠くて殴れない
2.腹は腕に守られていて殴れない
すなわち、初期条件が相手の攻撃(≒選択肢)を封じる形になっていると推察でき、従って、メイウェザーを殴るためには相手は一手間二手間が必要になると推論できます。
そこがミス(≒カウンター)の温床になると考えられます。
経験がない場合は想像するのが難しいと思いますが、強い選手、例えばトップアマや強い外国人は距離が遠く、かつ上半身が潰れいて殴れる面積が小さく感じます。
立ち方に隙がありません。
それは踏み込むのがストレスになるほど。その後ろ向きな感情は自己強化的にミスの温床となります。
恐らく、メイウェザーはその強化版。
また論理的に、選択肢が多いほど戦略上は有利になります。その対偶「選択肢が少ないほど不利」も真です。
すなわち、ガードは下げているが、メイウェザーの守りは論理的には強固だと言えます。
子供の頃に遊戯王をやってたなら分かると思います。
墓地肥やし(≒選択肢を増やす)戦略が圧倒的に強い。だから墓地肥やし戦略をとれば小学生相手なら無双できる。
地味な割に、手札を増やしたり墓地を肥やしたりにはやたらコストが要求される理由です。
閑話休題。
上記の「戦略は相手の選択肢を減らすこと」との解釈は思考を始める足場としては有用だと思います。



メイウェザーのフィリーシェルスタイルは、初期状態(≒構え)が相手の選択肢を削減し、一手間二手間のコストを要求する構造になっていると考えられ、すなわち、メイウェザーは比較的に有利なジャンケンをしていると考えれます。
これは細部を捨像し過ぎた乱暴な議論だとは感じますがますが、メイウェザーと同じような技術の構成である「フィリーシェル+アウトボクシング⇒高い優位性」、という論理の大枠は現実とも整合していると思います。
アウトボクシングスタイルのカネロやメイウェザー、ジェームズ・トニー、ドミトリー・ピログ、最近ならジャロン・エニスなど、超強豪にはこの形が多い理由を説明してくれていると思います。
ただし、腸腰筋が強いからフィリーシェルができる、も無視できない説明変数だろうとは思います。

要するに、メイウェザーの技術的な構成は、ボクシングという戦略ゲームにおいてはかなり有利なのではないかなと。
ちなみにフィリーシェルの由来は「フィラデルフィア人のシェルガード」。これが日本へ持ち込まれたのは動画が普及してからでしょうが、実は古くに開発され、過酷な競争を勝ち抜いてきた強固なディフェンス技術です。
その強固さは歴史が証明しています。仮に数万年間競争させたら、全てのボクサーはこの形に収斂するんじゃないかとすら思います。
白黒映像だとジョージ・ベントンが思い浮かびます。


必然としてのカウンター
結論までの前置きが長くなりました。
「カウンターが上手くなりたい」ないしは「ボクシングが上手くなりたい」と漠然と念じるのは時間の無駄。
『「強さ」とは〇〇だ。それを構成するのは✕✕と△△だ。そのためには□□をやる。』
と現象として起こる「強くなる」を個々の手順にまで落とし込むことで、その可能性を取り込めます。そうするのが建設的な大人の生き方です。
「あれがないこれがない」と悶えるのは餓鬼。
反復すれば強くなる、と言う餓鬼には近づかない。他人から搾取するだけの餓鬼にはボクシングや日本という社会から退場してもらう必要がある。でないと皆で飢えて死ぬことになる。

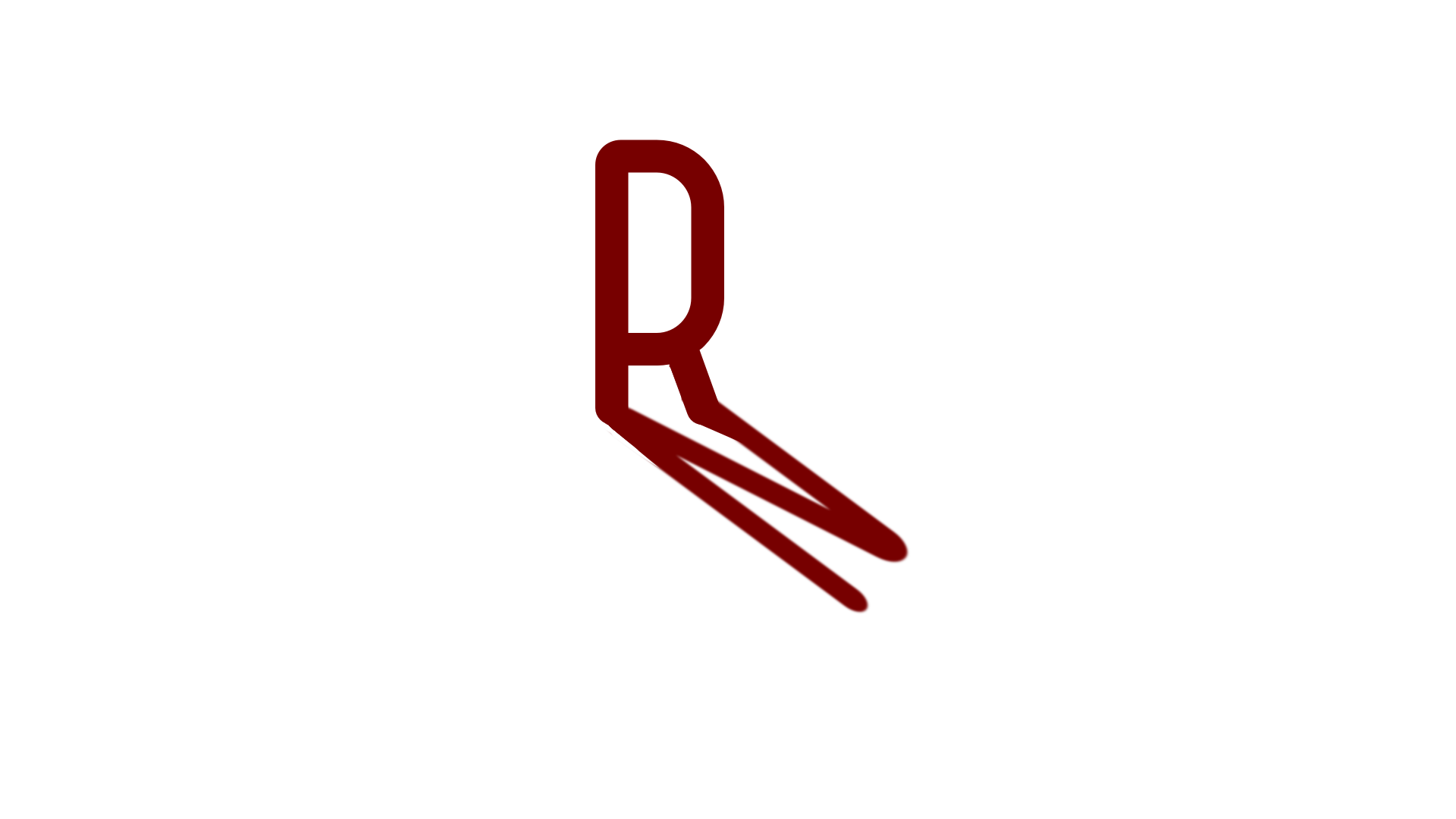
コメント