「キレがある or ない」「キレをだせ」「パンチは力じゃない、キレ」。
ボクシングに限らずスポーツをやったことがあればこの言葉は聞いたことがあるはず。
僕はこう思っていました。「じゃあお前、キレを生む具体的な要素を上げてみろ。曖昧な表現でマウントとった気になってドヤ顔してんじゃねぇぞ」って。
俗語なんで仕方ないとしても「キレ」って一応競技者、指導者レベルでも普通に使われる言葉です。
にもかかわらず、曖昧どころじゃありませんよね。
言ってりゃ素人でも玄人ぶれる程度には曖昧です。
中学時代にドヤ顔で洋楽聞いてた玉城を思い出します。
ここからが本題です。
例えば「ガードを上げる」ことの意味を厳密に定義できなければ、それを行うことの利点と欠点が見えてきません。
ガードを上げ続けることの欠点である「出力が落ちる」ことに悩まされていても因果関係が見えないから解消のしようがなく、余分な筋肉をつけて移動性、持久力を犠牲にするか、体力勝負の消耗戦を核に据えたようなスタイルを選択せざるを得ません。
※ガードを上げることを否定してはいません
物事を抽象化することで本質へと迫り、何が起こっているのかを細部まで眺めることができたなら、見える世界は一変します。
曖昧さを避ける癖は無駄なトレーニング、屁理屈からあなたを遠ざけ、あなたのポテンシャルを保護し、ひいてはあなたの未来を守ることへ繋がります。
「母指球信仰」「膝信仰」「ガード信仰」「手数信仰」…などなど。
曖昧さを回避することで、これらは拒絶できます。
キレの正体
キレ = 速さのメリハリ
恐らくですが、静と動のメリハリのことを俗に「キレ」と呼んでいるのだと思います。
静と動がクッキリしていた場合に「キレがある」と言いたくなるってことですね。
ただ、既述の通り「キレ」という俗語はあくまでも俗語であってイメージを元に感覚的に使われています。人それぞれ主観はことなるので、もしかするとあなたの「キレ」の意味と違うかもしれません。
上記の表現は僕が経験的統計によってこの意味で使われているだろうって「キレ」の意味を導きだしたものですのであしからず。
動きを作る「動」の重要性は直観的に理解されていますよね。
動き出しが強ければ当然動作は速くなることは想像できるので。
しかし「止める」動作、「静」については一般的には重視されていないと思います。
僕のブログの読者であれば「ブレーキ効果」による並進運動→回転運動の加速メカニズムを理解されているだろうとは思いますので詳しい解説はそちらに譲ります。
つまり漠然とではあるものの「静」の重要性に着目したのが俗に言う「キレ」ではないでしょうか。
まとめると「キレがある」とは「静」と「動」のメリハリのある動きのこと。
そして一般的には重視されるであろう「動」の裏に隠れた「静」の動きが表面化した場合、「キレのある動き」を生み出すということです。
もう少しキレについて深堀していきます。
パンチは力ではなくキレ?
「力(パワー)ではなくキレが大切」って言われますよね。
ここでの「力(パワー)」ってのが曖昧な感じがします。何のことを力(パワー)と呼んでいるのかを考えてみます。
「力」「パワー」が力学的な定義でないことは文脈から分かりますよね。
俗にいう「腕力で」って意味で使っていると思います。
もう少し厳密に言うと「筋力で」
力(パワー) = 筋力
ではないかってこと。
ここでの筋力には運動を制止する筋力は含まれません。
既述のように「静」は一般的には隠された部分であると考えられるので、あくまでも動き出しとなる「動」を作る筋力のことを指して「力ではない」と表現しているだろうってことです。
「力ではなくキレ」は「意識に上ってこない制止動作である『静』の方が大切なんだよ」と翻訳できました。
「パンチは力ではなく、キレ」は「止める動作を強めよ」と換言できると思います。
なぜ「キレ」という曖昧な表現になる?
恐らく
キレ = 静と動のメリハリ
並進(推進)→回転(制止)による身体の加速の巧みさを曖昧な「キレ」と表現しているのです。
これは自然なことだと思います。
運動の方法、原理をいちいち認識するのは僕みたいな指導者だけでいい。
指導者で知らなかったらヤバイですが。
でも体を意識的に制止しているのなら、どうしてそれを認識できていないのか?という疑問が起こります。
僕の想像の域を出ませんが恐らく、「制止動作」は意識的ではなく構造により半自動的に引き起こされているからです。
「制止によりキレを上げる」とは思っていないでしょうが「身体が流れないように」「バランスを崩さないように」みたいなイメージが間接的にキレを生み出している可能性はあります。
※キレを生み出せる構造であることが前提になります。
キレを生み出す構造とは「大腿骨を上半身の重さで押さえつけて骨格の構造を支えて立っている」「大殿筋を活性化するスタンス(足幅と足の向き)を作っている」「広背筋のSSCによって腕の運動を制止できる腕のポジションをとっている」大きくはこれらの要因が考えられます。
無意識に大殿筋により骨盤の並進が制止され並進→回転へ変換するスタンスが作れている、腕の並進を広背筋が制止し腕の並進→回転を引き起こす構造が作れているってことです。
ボクシングを始めた段階で上記の構造を作れる環境があったと考えられます。
指導者に恵まれたか、鋭い感性に従う強い意志を持っていたか。
言い換えると「始めに形成した経路が重要」です。
以上、長濱説でした。
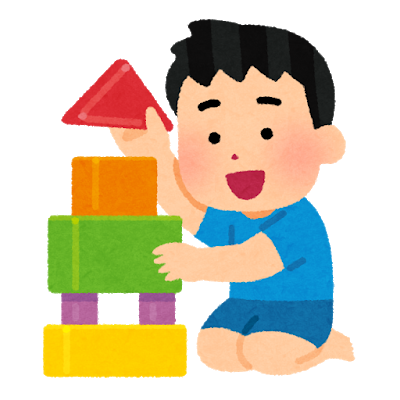





コメント