失敗確率>成功確率

物理法則のように厳密に定式化できるとかでもない限りは、未来の正確な予測はできません。
失敗確率>成功確率
ボクシングは必勝法が定式化されていません。
思うに、ボクシングはジャンケンのようなゲーム。つまり、必勝法を定式化できません。 だとするなら「絶対」や「こうあるべき」はあり得ない。
仮に必勝法と表現できる戦略があるとするなら、それは「試行錯誤を重ねて入出力の関係から法則性を炙り出していく」戦略、つまり「対応能力(戦略)」だと思います(感想)。
一流が試合前に「何が起きても対応する」と意思表明する傾向に気がついている人はいますか。
論理的には上記の必勝法(のようなもの)の話をしていると僕は考えています。

失敗しない為には
僕の経験と観察から、互いに未知の相手と戦う確率が高いボクシングの試合においては、失敗確率>成功確率の不等式が強調されます。
以上が妥当だと仮定します。
この場合は、「失敗しない」ことを前提に据えてしまうと、何もしないことが最も合理的です。
試行錯誤
これが「試行錯誤」「失敗は成功の母」の文脈。確率的に失敗は起こるよ。
また、認識のメカニズムから考えても「失敗は成功の母」は妥当です。
例えば登下校。
「寄り道」を繰り返す過程が近道を引き寄せます。
寄り道(失敗)を許容しない人は死ぬまで近道は見つけられません。
寄り道の比較は小学生に地形を把握させます。
ボクシングも同じ。失敗を繰り返すからボクシングという技術空間の地形が理解できます。
「ガード神」「顎引き神」を信仰し、その布教を熱心にしている信者にボクシングを説明する能力がない理由でしょう。
彼らは念仏を唱えているだけ。
ここでの「ボクシング」は、汎ゆる対象に言い換えられます。
つまり、「柔軟さ」「寛容さ」のような信念以外はヒトの認知能力を劣化させます(≒バカ)。
形(思考)を固定すること
ボクシングの入門者に失敗しない為のガード神話や顎引け神話を伝える前に、指導者は一度立ち止まって考える必要があるはずです。
ボクサー自身は、自身の信念が固定化しないように、常に自己批判を続ける必要があります。
殴られて痛い思いをして「ガード」や「顎を引く」の重要性を覚えた人と、記号としてそれを覚えた人の間には、自動車免許保持者と無免許車オタクのような差があります。
後者は現実の運転では使い物になりません。
運転はボクシングに言い換えられます。


鏡の前で形を整えさせる作業。
狭い教室の机上の紙に、空論を並べる作業を「知性」と錯覚させること。

話が大きくなったので戻します。
大切なのは「殴られないようにガードを上げる」ことでも「失敗しないようにバランスを保つ」ことでも、「ディフェンスは大切」と念仏を唱えることでもありません。
失敗した後で、即座にそれに対応できることです。
「形を守ること」がボクシングではなく、「形が崩れたのに対応すること」がボクシングでありボクサー。
ボクシングジムは、ボクサーに転ばないことではなく、転んだ後にどうするか?を教えるべきなんです。
また、「ガードを上げる」「顎を引く」の大切さと同時に、それが失わせる可能性も教えて上げるべきです。
失敗を繰り返しながら、ボクサーは自分の愚かさを知り謙虚になります。
失敗は誰にでもあることを知るから、失敗した他人に寛容になれます。
ジャージ・フォアマンのやモハメド・アリの精神性こそがボクサーです。
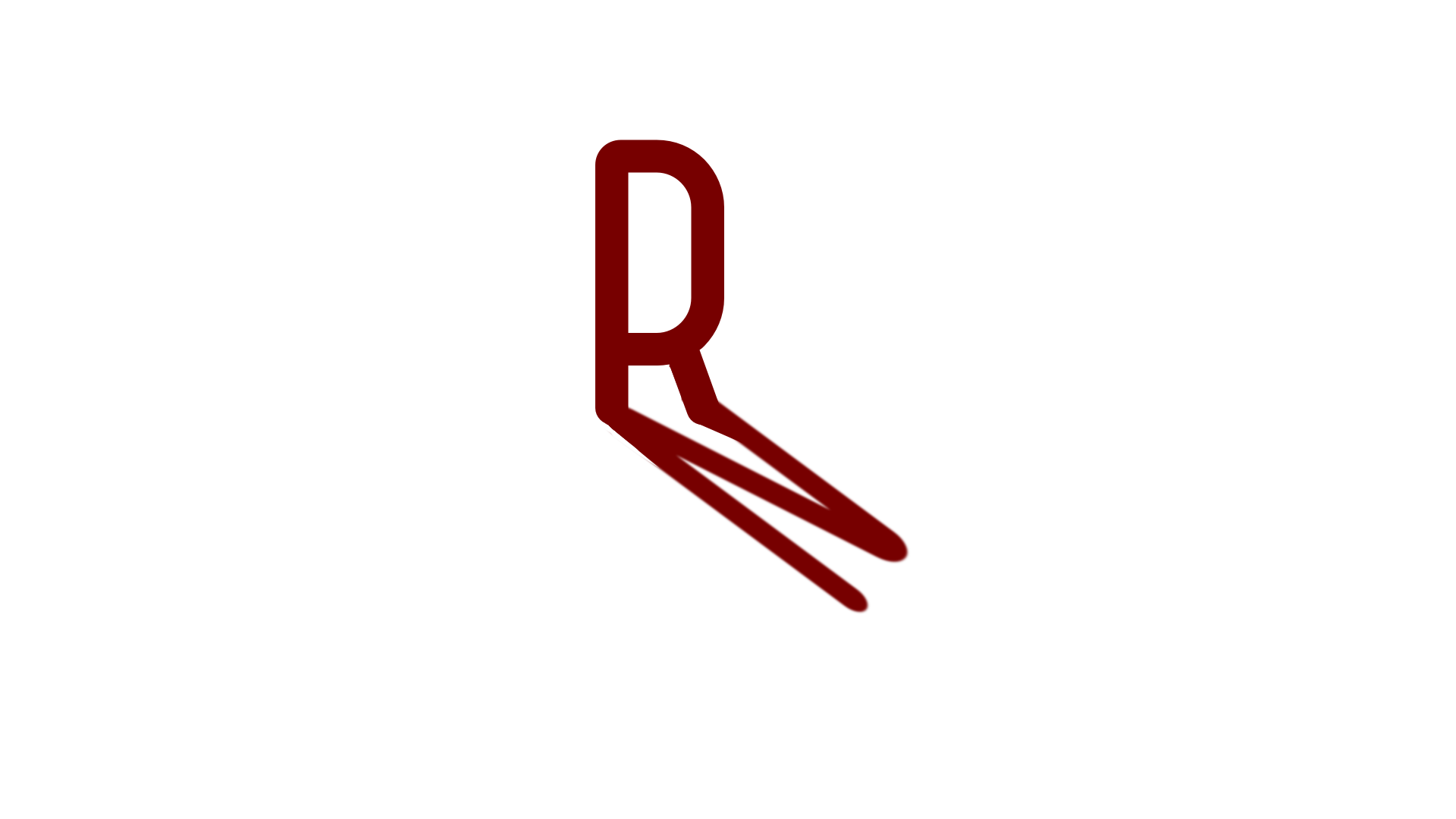
コメント