無理数って何やねんシリーズ。
有理数の連分数展開
連分数で無理数の性質の一端が見られるということなので、その方法を学びます。
準備として計算を練習します。

例題1)
$\frac{37}{28}$
展開
$\frac{37}{28}=1+\frac{9}{28}$(分数加法)
$1+\frac{1}{\frac{28}{9}}$(分数法則)
$1+\frac{1}{3+\frac{1}{9}}$(分数加法)
分母が1になったので終わり。
ついでにもう一つ。
例題2)
$\frac{35}{19}$(仮定)
$1+\frac{16}{19}$(分数加法)
$1+\frac{1}{\frac{19}{16}}$(分数法則)
$1+\frac{1}{1+\frac{3}{16}}$(分数加法)
$1+\frac{1}{1+\frac{1}{\frac{16}{3}}}$(分数法則)
$1+\frac{1}{1+\frac{1}{5+\frac{1}{3}}}$(分数加法)
有理数は分母分子が互いに素になるので、有限回の連分数展開で終わらせられます。
次は無理数
例題)√2の連分数展開
準備
(x+1)(x-1)(仮定)
(x+1)x-(x+1)(分配法則)
x²+x-x-1(分配法則)
x²-1(加法逆元)
(x+1)(x-1)→x²-1(→導入)
逆方向への演繹も成立するので
(x+1)(x-1)⇔x²-1…①
√2²=2(仮定)
√2²=1+1(自然数加法)
√2²-1=1(加法逆元)
(√2+1)(√2-1)=1(①)
$\sqrt{2}-1=\frac{1}{\sqrt{2}+1}$(乗法逆元)
$\sqrt{2}=\frac{1}{\sqrt{2}+1}+1$(加法逆元)
√2を定義する要素に√2がある再帰的な構造になっています。
よって
$\sqrt{2}=\frac{1}{\sqrt{2}+1}+1$
$\sqrt{2}=\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}+1}+1+1}+1$
これは無限に続けられます。
よって、
1,2,2,2…
規則的な構造であると言えます。
このように連分数で処理すると、無理数は規則的に動くものとそうでないものに分かれるようなのです。
eやπには規則性がないようです。
こう聞くと、無理数のその先の数もありそうに感じますし、また、認識できる有理数ではなく無理数が数の本質であるような、まるで有理数は無理数の周りに張り付いている影のようなものである気がしてきます。
ヒトが知覚していない世界こそが本当の世界。




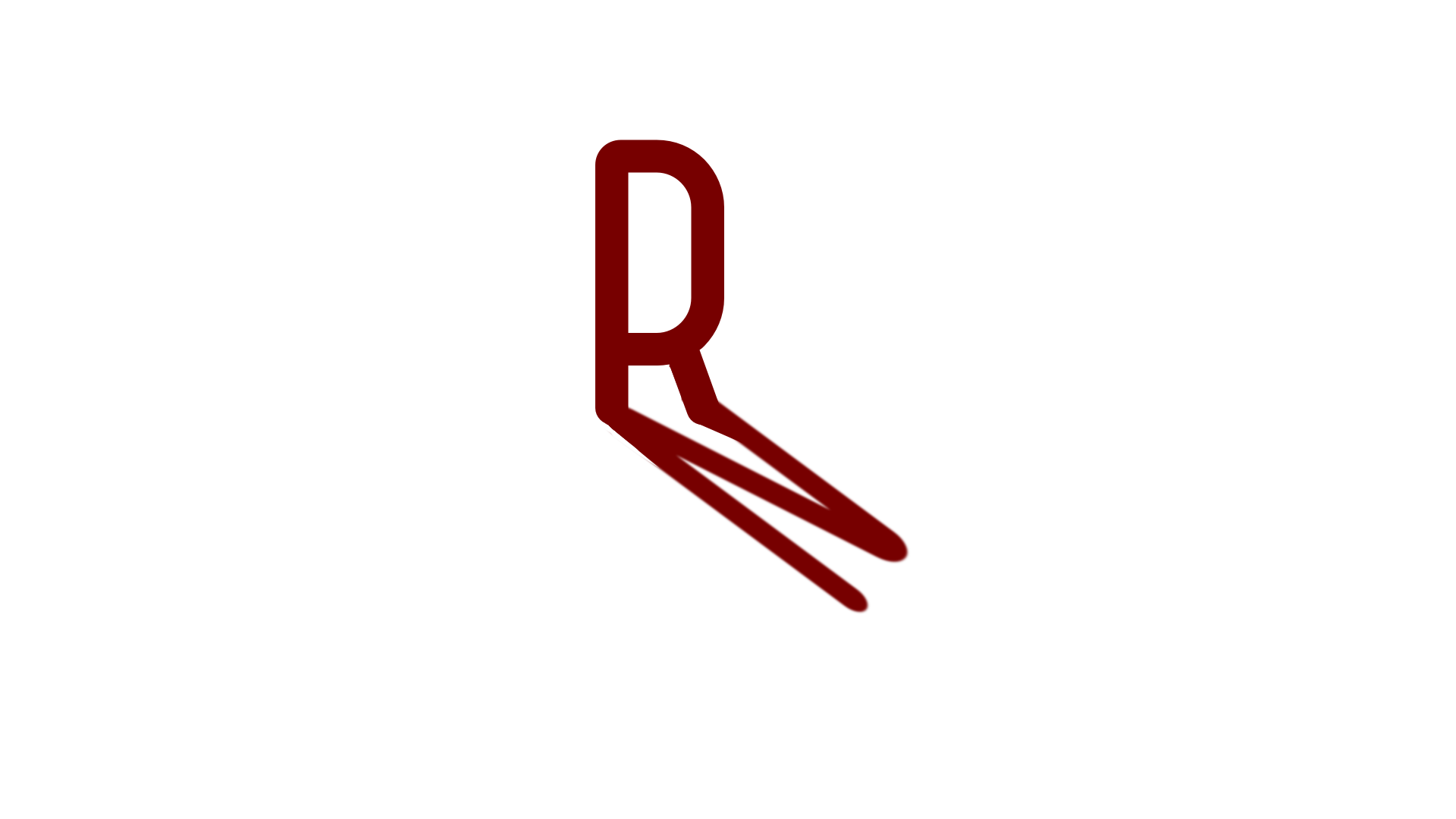
コメント