モンティ・ホール問題
<投稿された相談>
プレーヤーの前に閉じた3つのドアがあって、1つのドアの後ろには景品の新車が、2つのドアの後ろには、はずれを意味するヤギがいる。プレーヤーは新車のドアを当てると新車がもらえる。プレーヤーが1つのドアを選択した後、司会のモンティが残りのドアのうちヤギがいるドアを開けてヤギを見せる。ここでプレーヤーは、最初に選んだドアを、残っている開けられていないドアに変更してもよいと言われる。
ここでプレーヤーはドアを変更すべきだろうか?引用ウィキペディア
最初にあなたが選べるのは三つ。そして、その中の当たりは一つ。
よって、最初に選んだドアを「変更しない」場合は当たる確率は1/3。
次にドアを「変更する」場合を考えます。
初めに1/3の当たりを選んだ場合は、残りは全てハズレ。
つまり、「変更する」を選んだ場合は初めに当たりを引く確率=ハズレの確率となるので、ハズレる確率は1/3。
次に初めにいずれかのハズレを選んだ場合。
司会者は初めのドアを開けた後で、ヤギのいる”ハズレを”教えてくれます。
つまり、ハズレを引いた後にドアを変更すれば必ず当たります。
従って、「変更する」場合は2/3で当たります。
既述の通り、「変更しない」場合は三通りから一つを選ぶのと同義なので、当たる確率は1/3。
「変更する」場合は、初めにハズレを引く確率と同じなので2/3。
よって、「変更する」を選ぶ場合は勝つ確率が二倍になります。
合ってる?間違えてたら教えてください。
何故混乱するか
混乱の分岐点は「司会者がハズレを知っていることを考慮できたか?」だと思います。
問題文の通りに「司会者がハズレを知っている」を考慮するなら、「変更する」が二倍有利になるのは分かります。
仮に司会者がランダムにドアを開けるなら確率は変わりません。
恐らくは、問題文が自己言及のような構文になっているから、つまり、あなたの選択を参照して司会者が選択を変更する構文になっていることが混乱の原因ではないかなと。
主観的には初めに確率は確定している気がする。が、文の構造は最初の選択を参照して結果を変える。
「「」の中は嘘です」
この構文は論理的に真偽が定められない。この混乱に似ている気がします。
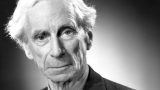


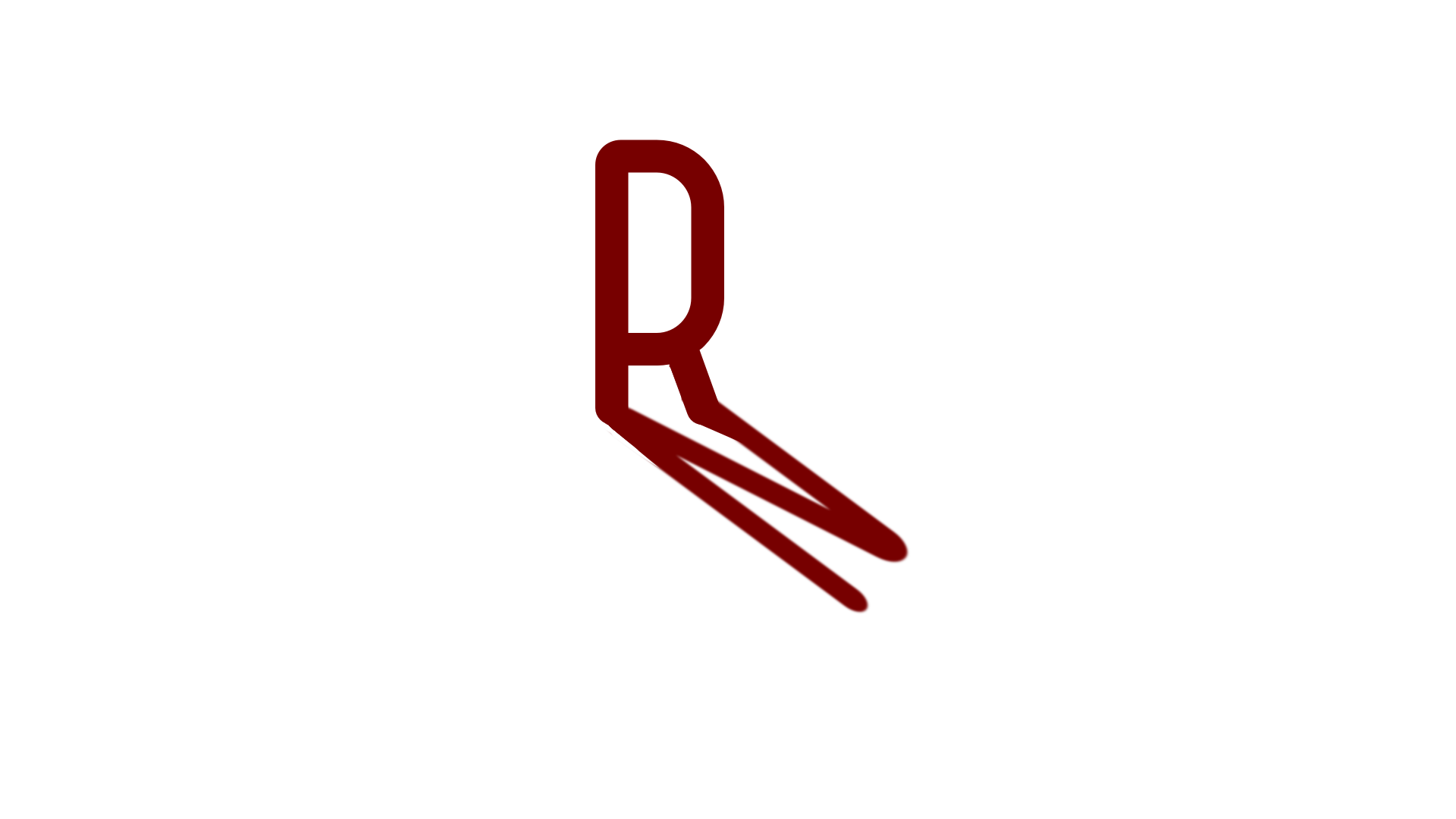
コメント