スタンフォード大学の研究チームは、心拍数が上がると不安な感情に関連した行動が起こりやすくなる現象をマウスの実験で発見した。心拍数の変化が脳の特定の領域に影響を及ぼし、マウスが不安を感じたときに見られる行動を引き起こした。感情によって体の反応や行動が変化するだけでなく、心拍という体の変化によって感情が影響を受ける仕組みも存在する可能性があるという。
引用 日本経済新聞
不安を感じると、心拍数が上昇することがあります。これは、不安や緊張によって交感神経が活発になり、心臓の鼓動が速くなるためです。通常、安静時の心拍数は50~70回/分程度ですが、不安や緊張を感じると100回/分を超えることもあります。
引用AI
恐怖が先にあるのではなく、心拍数の上昇や瞳孔の拡大が先にあり、それに呼応して恐怖という感情が生成される。
考えてみれば当たり前な気はしますが。
視覚や聴覚、触覚などから入力される刺激を起点に反射が起こり、それに紐付けられた記憶や遺伝子の性質が呼び出される。
それがまた視覚や聴覚を内部から刺激し…の自己強化的な循環が所謂「恐怖」。
心拍数などが「恐怖」の閾値を超えると逃走反応が起こり、「戦おう」という意思が起こらなくなる。
でかい犬を見る→瞳孔が開く→心拍数が上がる→恐怖を覚える→瞳孔が開く→心拍数が上がる…
環境とあなたの遺伝子、脳に保存された記憶との相互作用があなたの意思と判断を決定します。
好きになる人を選ぶことができないのと同じ。好きになった人が好きな人。好きになろうとしてなれるものではない。
同様に、「恐怖」「不安」は意思だけではどうにもならない。
「今日はやるぞ」
と念仏を唱えのは無駄。行動を変えるのは心。心を変えるのは環境。だから心や行動を変えるには環境(≒考え方やトレーニング)を変える必要がある。
ベンジャミン・リベットの実験は、行動の前に脳内で無意識的な活動が起こることを示し、自由意志の存在に疑問を投げかけました。
1983年、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の生理学者、ベンジャミン・リベットは、被験者が手首を曲げるなどの簡単な動作をしようとする直前に、脳内で「準備電位(Readiness Potential)」と呼ばれる無意識的な電気信号が立ち上がることを発見しました。
引用AI
嫌いな奴の側にいては、いつまでも脳はやる気にならない。
あなたの経験とも整合するはず。
体力がないと戦う意思が生理的に起こらない。
老人が頑固なのは、新たな考え方を受け入れるだけの体力(≒心肺機能)がないから。
体力のない若者も然り。心臓に負担をかけたくない本能は消極的な選択をする。
意思を操作するには自分のいる環境やその土台である体力を整備しなければならない。

心拍数が上がる⇄不安
この循環が起こらなければ不安を感じない、と拡大解釈できます。
小学生のマラソン大会に出場するのを想像してください。恐怖も不安もないはず。表彰が待ち遠しいだけ。
ランニングでは、心拍数が上がると「もういいかな」などと弱気になります。これと同じことが試合中にも起こると考えるのが自然でしょう。
結論。恐いなら心肺機能を鍛えてみては?
少しは不安を感じにくくなるかもしれない。上手くいかないにしても、それを次の手を考える足場にはできる。
これはあくまで一例です。
大切なことは、「恐怖」や「不安」を漠然とさせたまま放置しないこと。その実体を捉えようと藻掻くこと。
仮にそれを捕まえられたなら、コントロールできます。
僕は子供の頃から、自分の不安心や恐怖心に悩まされ続けています。
子供の頃は不安症からくるチック症で心療内科を受診したり、幼稚園の先生が小学校卒業まで連絡くれるほど臆病だった。
プロボクシングをやっていた、しかも東洋太平洋チャンピオンだった、などと聞くと、子供の頃の僕を知っている人は驚きます。
自分の臆病さを認めないボクサーは本当に多いです。いつまでも試合でビビっている。控室がみっともない。
自分が臆病なことを認められたら、恐怖の正体を捉える努力ができます。そうしたら、時間はかかってもきっとコントロールできます。
下のダマシオ先生の本は、恐怖を克服する方法に示唆を与えてくれます。
10代の頃から無くしては買って、を何度も繰り返す程度には大切にしている本です。
デカルト「我思う、故に我在り」
ダマシオ「デカルト、それ科学的には誤りだよ」



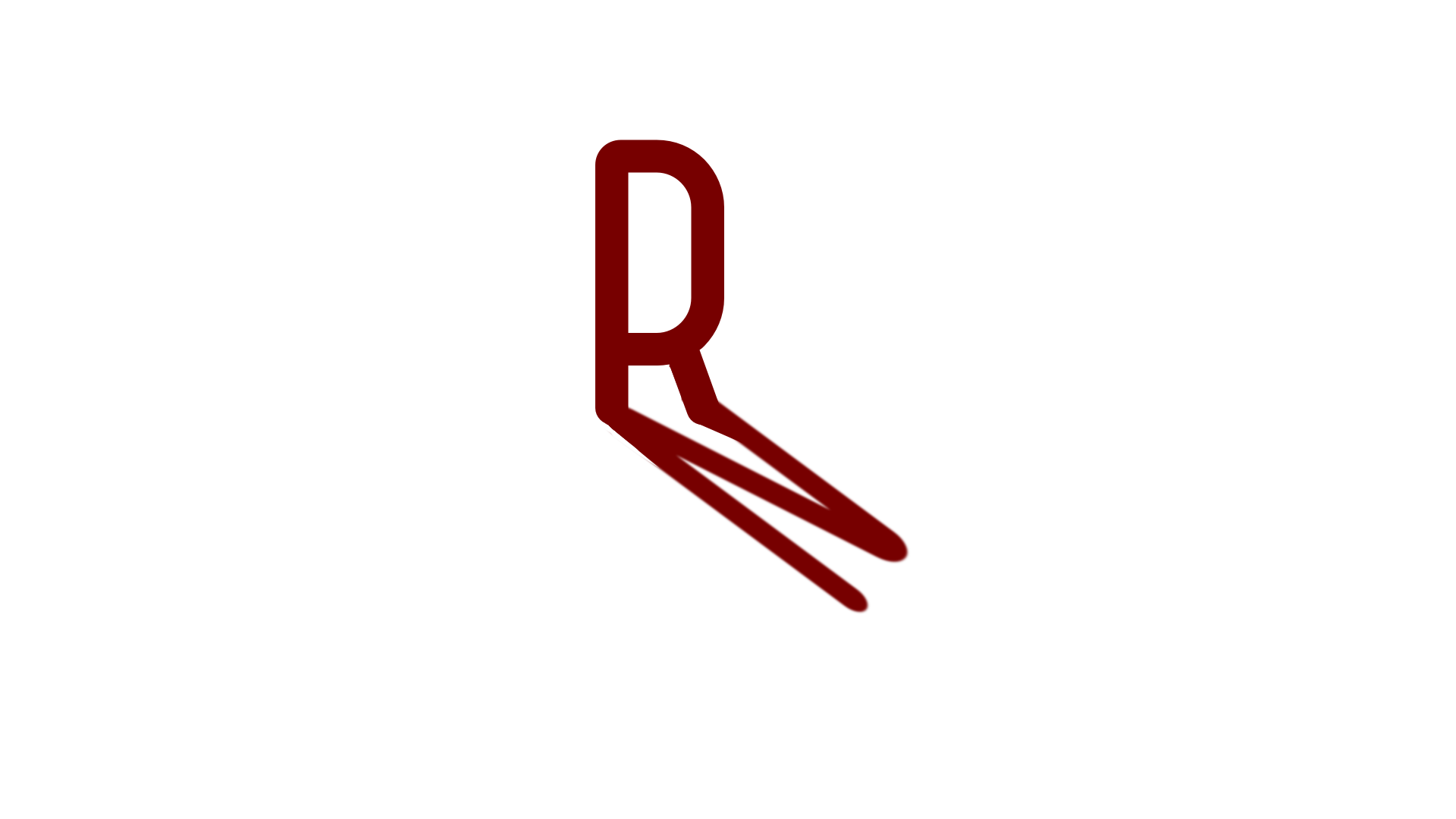
コメント