
黄金数って面白いなあとなると、必然的に円周率にも関心が向きます。円周率には面白い性質はないのだろうかと。
円周率(えんしゅうりつ、英: Pi、独: Kreiszahl、中: 圓周率)とは、円の直径に対する円周の長さの比率のことをいい[1]、数学定数の一つである。
円周
0円の周長 c は、直径を d とすると、
c = πd
と表される。直径の半分である半径を r として、
c = 2πr
と表される場合も多い。
円
数学において、円(えん、英: circle)とは、平面(2次元ユークリッド空間)上の、定点O(オー) からの距離が等しい点の集合でできる曲線のことをいう。
義務教育では「√2は有理数ではない」の証明は何となくフワッとやった気がしますが、円周率に関する証明はなく、「円周率はこう。覚えろ」だったと思います。
そもそも円周率とはなんぞやと。
ウィキペディアによればπ(円周率)は円周と直径の比のこと。
$π=\frac{2πr}{2r}$
円の定義より、定点Oと半径を決めれば円周は決まります。
つまり、円周率は円そのもの。
円には半径と円周(定点)以外の情報はありません。
仮に乗法でそれらをまとめてしまうと値が大きすぎて使い勝手が悪いので、除法を用いたのだと思います。
昔の偉い人がそう決めてしまったから円周率は3.14…なだけ。
円周率が3.14…なのは、水が100度で沸点する理由と同じ。6.28の世界線もある。
「直径と円周の比が円周率!」と勝手に決めたものが様々な所に現れるのが、数学的、哲学的に面白いのだと面白います。
※「勝手に」とは言ったが、幾何学的には恣意性のない重要な関係ではあるはず。
結論。円周率は、円の定義を別角度から見たもの。
とりあえずはこんなもんで理解しときます。
よし、πが無理数である証明をしよう、と試してみましたが難しい。実数の定義を学んでいる分際には解析学は手に負えそうもないので、πが無理数である証明は先の楽しみにとっておきます。
円はイデア。というか数学はイデア。
「イデア」は、主に哲学におけるプラトンの概念であり、現実世界の背後にある完全で永遠不変な本質や理念を指します。
引用AI



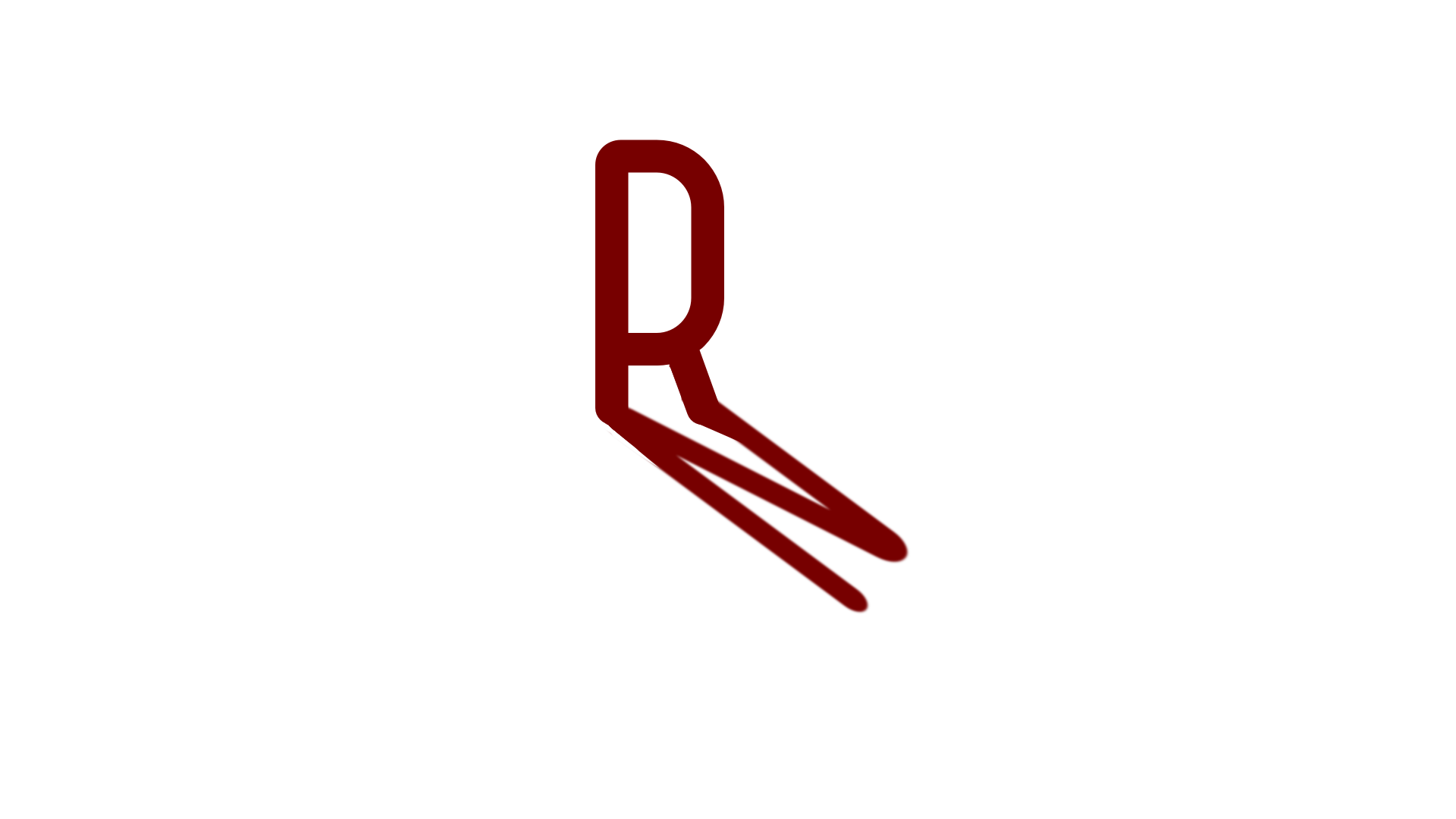
コメント