一緒に論理的思考能力を鍛えましょう。
リンダは31才、独身、率直な性格で、とても聡明である。大学では哲学を専攻した。学生時代には、差別や社会正義といった問題に深く関心を持ち、反核デモにも参加した。
どちらの可能性がより高いか?
- リンダは銀行窓口係である。
- リンダは銀行窓口係で、フェミニスト運動に参加している。
引用ウィキペディア
ヒント。
問題は”確率”を聞いています。
「文の意味」を正確にを捉えてください。「あなたがどう思うのか(感想)」ではなく、事実について尋ねられています。
答え
この質問を受けた人の大多数が選択肢2を選んだ。しかしながら、2つの事象が同時に(in conjunction:合接して)発生する確率は、そのどちらか1つの事象が発生する確率よりも、低いか等しいかのいずれかである。形式的には、2つの事象AとBについて、不等式を次のように書くことができる。
$\displaystyle \Pr(A\land B)\leq \Pr(A)$
$\displaystyle \Pr(A\land B)\leq \Pr(B)$
引用ウィキペディア
合接の誤謬(ごうせつのごびゅう、英: conjunction fallacy)もしくは連言錯誤とは、一般的な状況よりも、特殊な状況の方が、蓋然性(確からしさや発生確率)が高いと誤判断することである。リンダ問題としても知られている。形式的誤謬(formal fallacy)の一つである。”conjunction”には、合接、連言、論理積[注釈 1]などの訳語がある。行動経済学や行動科学などの分野で非常に強い影響力を有しており、主観確率における重要な概念である[1]。
AI による概要
主観確率とは、ある人が事象の発生をどれくらい信じているか、という主観的な確率のことです。
引用AI
「リンダが差別や社会問題に関心があった」という文に引きづられて、恣意的な文(主観確率)を挿入しませんでしたか?
形式的に「確率だけ」を考えるなら、要求される条件は少ない方がそれは高そうだ、と考えるのが妥当です。

「銀行員である」と「フェミニストである」という事象の確率は独立しています。
従って、例えば前者を10%、後者を5%とした場合は、合成した確率は0.5%となり、いずれよりも低くなります。
いずれかが100%だと仮定しても、一方を単独で選択した場合と確率は同値となります。
すなわち正解の確率を高めるなら、「リンダは銀行員である」以外の選択はあり得ません。
これは合成の誤謬と呼ばれ、SNS、YouTube解説系で頻繁に見れる、根拠不明なただの「願望」を、まるで事実であるかのように修飾して推論の過程に紛れ込ませる誤謬(詭弁)の典型です。
修辞学(しゅうじがく)とは、効果的なコミュニケーション、特に弁論や説得の技術を研究する学問です。古代ギリシャに起源を持ち、古代ローマを経て、現代まで様々な分野で応用されています。修辞学は、単に言葉を美しく飾るだけでなく、聴衆の感情や思考に訴えかけ、理解や納得を得るための技術体系です。
引用AI
恐ろしいのは、本人がそれに気がついていないだろうこと。
視聴者を巧みに騙している可能性もあるが。
「リンダがフェミニストであってほしい」は聞き手の願望(≒感想)です。
ジョージ・ポリア「知らないことは推論に用いるな。知っていることだけに集中しろ」
何故、数学者が正解を導けるのかを教えてくれます
論理学の専門書ですが、入門にはオススメです。論理学や数学が何をしているのかの全体像を掴めます。
また、その限界も垣間見れます。
面白い問題が多いので、遊びながら論理的思考を鍛えられます。「こうならこう、こうならこう。よって、こう。」という将棋に近い楽しさ。
問題を解いて遊びながら確率が学べます。
勝つ確率を確定させられれば、損失を予測できます。
損失を予測できることは、は自信を構成する変数だと僕は考えてます。
頭がいいヤツは「失敗すると損失はこれ。成功するとこれ。だから、やった方が得。」が計算できるから、つまり、損失を予測できているから自信満々なわけです。
遊びながらを確率ってこんな風に計算するのか〜を学べます。
今後も時々面白い問題を見つけたら紹介しますね。





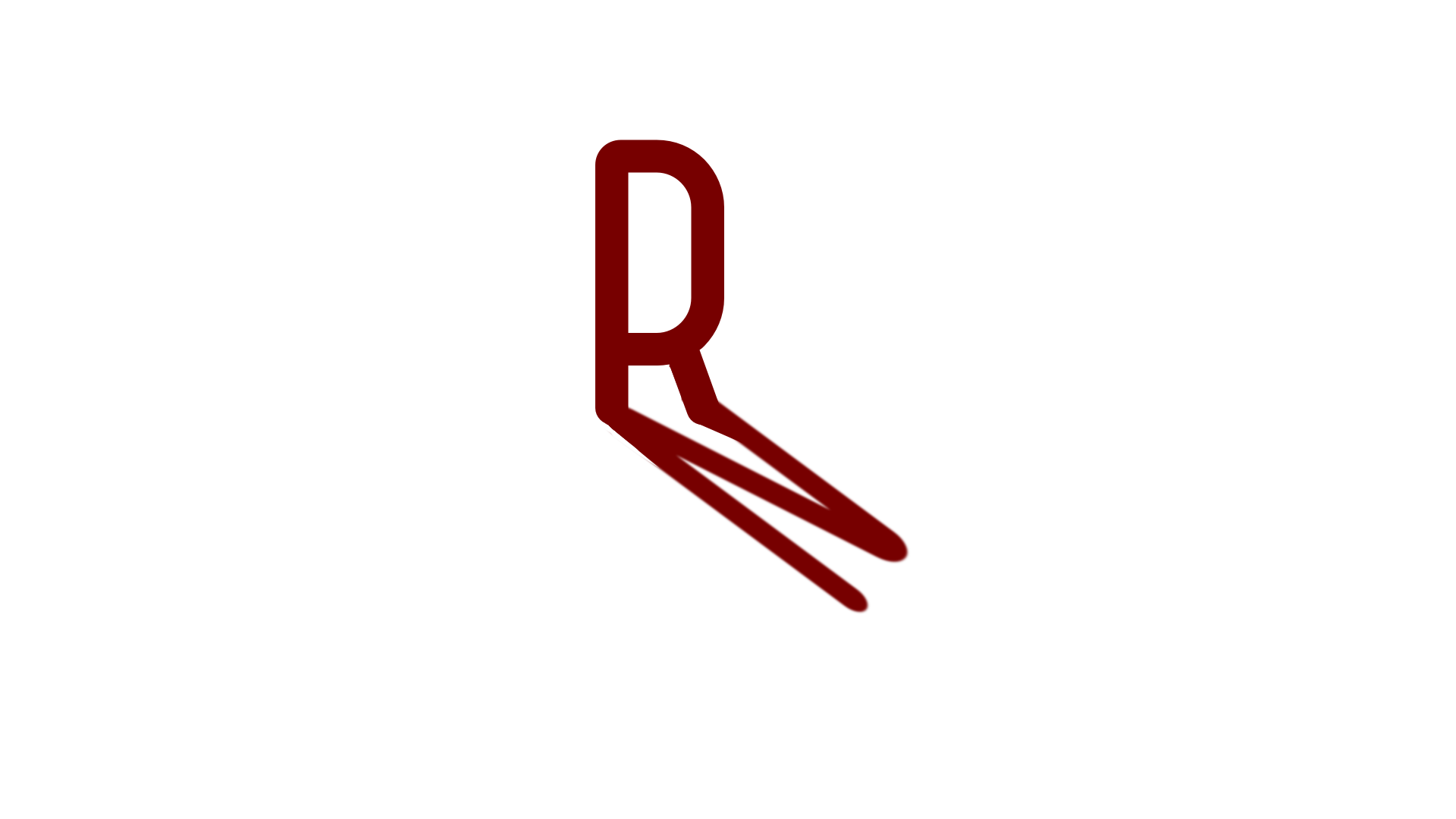
コメント