
べき乗
実数 x の正整数 n 乗は、素朴には、n 個の x を掛け合わせたものである。厳密には、次のように再帰的に定められる。(∗)x¹:=x,(∗∗)xn+1:=xⁿ×x(n≥1).x0
を定義する場合には、関係式 (∗∗) が n = 0 でも成立するように定義を拡張するのが自然である。
一意性とは数学分野において、注目している数学的対象が「存在するならばただ一つだけである」或いは「ただ一つだけ存在している」という性質である。 これら二つの主張は論理的な意味が異なるが、文脈によってどちらの意味かは異なる。
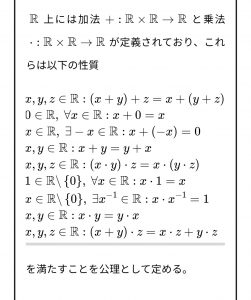
実数の定義引用WIIS
べき乗の一意性
「べき乗の一意性」が呼び方として正しいのかは不明ですが、調べるのが面倒なので、とりあえず底と指数を共有するべき乗が、演算の結果を必ず同じ場所へ送る性質を便宜上そう呼びます。
$(1∨0)≠a⇒a^{m}=a^{n}⇔m=n$
底を共有するなら、べき乗は一意的であってほしい、という願いがあります。
まずは、証明の基本である背理法が機能しないかを確かめます。

証明
$a^{m}≠a^{n}(仮定)
m=n$(仮定2)
$a^{n}≠a^{n}$(代入法則)
⊥(矛盾)
$m≠n$(背理法)
$a^{m}≠a^{n}→m≠n$(→変形)
底を共有するべき乗の結果が異なるなら、その指数は異なる。
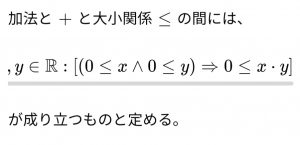
乗法律引用WIIS
まずは乗法の大小関係の復習。
[0<x<y,z](仮定)
0<(y-x)z(乗法律)
0<yz-xz(分配法則)
xz<yz(加法逆元)
x<y∧0<x,y,z→xz<yz(→導入)①
乗法は大小関係を保存します。
$[1<a]$(仮定)
$a^{n}・1<a^{n}・a$(①)
$a^{n}<a^{n+1}$(乗法単位元と∗∗)
$1<a→a^{n}・<a^{n+1}$(→導入)
1より大きい実数のべき乗は指数が自然数なら、その大小関係を保存します。
$[a<1]$(仮定)
$a^{n}・a<a^{n}・1<1$(①)
$a^{n+1}<a^{n}<1$(∗∗)
$a<1→a^{n+1}<a^{n}$(→導入)
同様にx<1の場合も指数が自然数なら、底を共有するべき乗は、指数の大小関係を保存します。
1<aの場合もa<1の場合もべき乗は一意に大小関係を保存します。
従って、順序が定められない場合、つまり、¬(x<y∨y<x)の場合は、三分律より、x=yとなります。
よって、べき乗は一意に順序を定めます。
$2^{n}=2^{m}⇒n=m$
底を共有するべき乗の結果が同じなら、指数は等しくなります。
計算機に同じ値を入力するなら、計算の結果は常に等しくなります。仮に入力の度に結果が変わるなら、その計算機は壊れていると判断できます。
例外)
上記の二つの照明はいずれも1<x∨1<xの場合にのみ成立します。
底が1か、0の場合は前提から除外されています。底が1の場合は指数の自然数nを限りなく大きくしても、乗法単位元の性質より、常に1へ送られます。
例)1⁵=1²=1
また、0との乗法は実数には定義されていません。
補足
0と任意の実数との乗法が0となるのは定理です。
0との乗法
a(仮定)
a+0(加法単位元)
a(仮定)
a・1(乗法単位元)
a(1+0)(加法単位元)
a+0a(分配法則)
加法一意性より
a+0=a+0a
が成り立ちます。
よって、任意の実数と0との乗法は0。
ミクロの過程は様々に分岐するから予測不可能なんけど、マクロの結果だけは予測できる。
この世界は、始まり方と終わり方だけが決まっていて、過程だけが無秩序に動いているシミュレーション世界。
ヒトの認知能力がそうなだけで、世界は別(形而上)にある説を推すが。



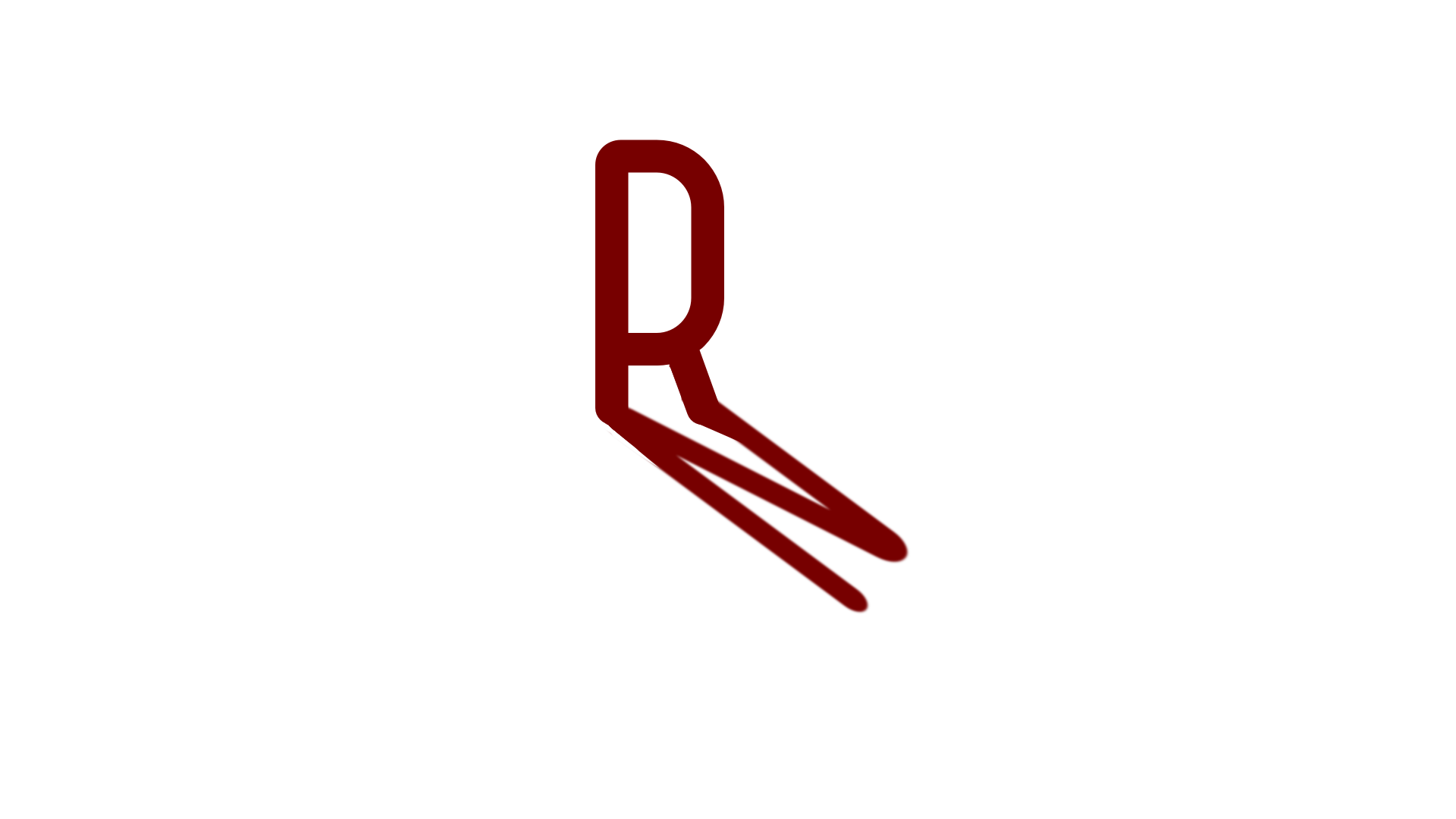
コメント